“楽しい”が交通事故を減らす?認知メカニズムの研究が描くひととクルマの未来
加藤 正隆
ひと研究(データアナリスト・ソフトウェア)
2017年新卒入社
パナソニックオートモーティブシステムズは、社員一人ひとりの成長と自律的なキャリア形成を支援するため、さまざまな人事制度や研修プログラムを整えています。
加えて、各部門でも担当事業や専門性に沿った独自のキャリア支援を行っています。
今回は、2017年新卒入社 加藤正隆さんへインタビューしました。何事も“楽しむ”ことを大切にする加藤は、開発本部 統合制御システム開発センター HMI開発部 開発1課のスペシャリストとして、ひとの認知メカニズムの研究やヘッドアップディスプレイ開発に取り組んでいます。最新の知見を取り入れながら“楽しく安全に運転できる社会”をめざす加藤が語る、仕事のやりがいとは。
ひとの認知メカニズムの解明が交通安全につながる。鍵は“楽しく運転できること”

──現在の業務内容を教えてください。
ひとの認知メカニズムの研究開発に従事しています。近年、クルマには自動ブレーキなどの運転支援機能が数多く搭載されていますが、交通事故の多くは依然としてドライバーのミスが原因となっています。
この問題を解決するために、私たち研究チームは「ひとの予測特性」に着目。ひとは物を見る時、無意識のうちに次に何が起こるかを予測しながら認知しています。それによって効率的な情報処理が可能になる一方で、予測を誤ったり過信したりすると見落としや思い込みにつながってしまう。そこで、この現象を引き起こすとされる視覚の特性を取り入れた深層学習モデルを活用し、「こういう交通シーンではどんな見落としが起こるのか」「どんな支援をすれば見落としを防げるか」など、ドライバーの認知ミスを分析しています。
また、ひとの認知メカニズムの研究で得られた知見を基にしたヘッドアップディスプレイ(以下、HUD)の開発にも携わっています。HUDは運転中にフロントガラスに直接情報を表示することが可能な機器で、従来のカーナビと異なり、運転時の視線移動を最小限に抑えながら車速やナビ情報を確認できるメリットがあります。
しかし、表示が過剰になると、前方は見ていても周囲への注意が散漫になるリスクも。そのため、認知メカニズムの理論にもとづいて運転の邪魔にならないながらも必要な情報を表示する方法を検討し、安全性の評価を含めた開発提案を行っています。新しい技術のため、適切な表示方法や安全性の知見は発展途上。われわれの手で、安全かつ有益なものをつくりたいと考えています。
──研究チームはどんな雰囲気ですか?
ベテランのリーダー1名と、私と後輩の3名体制のチームです。研究好きで話好きなメンバーが多く、最近ではひと研究×AIの活用可能性などについて日々活発な議論を行っています。また、社内の事業部や共同研究先の先生方とも連携しながら研究を進めています。
──研究で重視しているポイントは何ですか?
ドライバーのミスを減らすための運転支援では、“わかりやすい”と“使っていて楽しい”の2点が重要だと考えています。運転のミスを減らすことを勉強に例えると、わかりにくい参考書でやる勉強は中々成長が見込めず、勉強そのものを楽しく感じるようにならなければ長い期間で成長し続けることは難しいと思います。
それと同じで、運転支援はまずわかりやすくある必要があり、認知ミスが起こりやすいところをリスクに応じて表示を変えたり、似たような場面でも変化をつけたりするなど直感的にわかりやすい表示を行うことで、支援の効果が向上すると考えています。この実現には、ひとがどのように認知を行うのかのメカニズムに基づいて効果的な方法を考えていく必要があります。
加えて、わかりやすいだけでなく、安全運転を行うこと自体が楽しく感じるような仕掛けが実現できれば、ドライバーの成長を長期にわたって促すことができ、継続的に認知ミスを減らすことにつながると考えています。
そこで、われわれはゲーム設計の理論や行動変容のデザインなども取り入れながら、ドライバーがいかにストレスなく、楽しみながら自然に安全な運転ができるようになるか、ひとの特性を理解し、より効果的な仕組みづくりをめざして研究を行っています。
責任重大だからこそ社会貢献できる。入社して知ったモビリティ領域での人間工学の意義

──人間工学に興味を持ったきっかけを教えてください。
大学時代は情報工学を専攻し、当初はソフトウェアやコンピューターに興味を持っていました。ある時、「男性用トイレに的当てのようなシールを貼ったところ、自然にトイレをきれいに使うようになり、注意喚起の貼り紙より効果があった」というニュースを見てとても感心したんです。そのほか、趣味のゲームをしている時に、画面の見た目の変化だけでユーザーの印象が大きく変わることにも同様のおもしろさを感じました。
さらに、いくら高度な機能を持つ製品でも、使いやすい設計でないと多くのひとが使いこなせないという課題に気づき、グラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)や人間についての理解を深めた上でものづくりをする必要性を感じるようになりました。
──就職活動ではどのような企業を検討していましたか?
主に家電や電機メーカーを中心に活動を行っていて、自動車に限定はしていませんでした。その中で、パナソニックのインターンシップで画面設計やアプリ開発などの実務を経験した時に、仕事のおもしろさに加えて、職場のひと柄の良さや歓迎的な雰囲気に惹かれ、ここなら活躍できそうだと感じて入社を決意しました。(※)
──2017年に入社して、大変だったことを教えてください。
入社後は、ヘッドマウントディスプレイというVRゴーグルに関する研究に従事していました。当時大変だったのは実験で、実験中のけがは社員だけの問題ではなく、会社の社会的信用にも関わるため大きな責任が伴います。
そのため、たとえば実験環境での転倒やVR酔いなどへの細かな安全対策も徹底して行っていました。一見面倒くさいと感じることでも、それらは会社が積み上げてきた安全の資産。社員をしっかりと守り、安心して実験できる環境がある当社の文化だと思います。
──入社後、仕事への向き合い方や行動で変化したことはありますか?
人間がつかいやすいものづくりに携わりたいという思いで入社を決めたのですが、入ってから、自動車はUIが使いにくければ事故につながる可能性があるなど、私の思いとマッチしている領域だと気づきました。さらに産業規模としても大きいため、より広く社会貢献できる可能性を感じ、しだいにモビリティ領域への興味が深まっていきました。
もっとも大きな変化は、“仕事を楽しむ”ことを大事にするようになったこと。学生時代は必要なタスクを論理立てて進めることが仕事における能力だと考えていました。しかし、休日も学会に参加している先輩など、実際に成果を上げているひとたちはみんな仕事を楽しんでいると気づいたんです。
だからこそ高いモチベーションを維持でき、新しいアイデアも生まれやすくなり、結果的に深い知見や周囲からの信頼獲得にもつながる。私自身も、興味のある「ひとの認知機能の研究」というテーマに携われており、ユーザーを楽しませることを考えられること自体を楽しいと感じているので、楽しみながら仕事に取り組めていると感じています。
※ 2017年にパナソニック株式会社に入社後、2022年にパナソニックグループが持株会社制に移行したことに伴い、車載事業の事業会社として発足したパナソニック オートモーティブシステムズ株式会社に転籍
学会での発表や特許出願、事業貢献──これまでの知見が拓いた道

──これまでの実績について教えてください。
研究チームで取り組んだ、ひとの認知メカニズムの研究成果を自動車技術会で、4回ほど発表し、論文掲載も実現しました。たとえば「ひとの視覚をシミュレートする深層学習モデルを用いた交通ヒヤリハットの要因分析」では、ひとの予測特性をAIモデルに実装し、交通ヒヤリハットの映像を分析することで、事故に至るメカニズムの解明をめざしました。
専門家の方々からも高い関心をいただき、部門委員会での招待発表の機会をもらったり、著名な先生から「この研究のファンです」とお言葉をかけてもらったり。それは非常に嬉しかったですね。また、研究の成果を特許としても出願しており、国内外で5件ほどの出願を行っています。
──これまで印象に残っている出来事は何ですか?
最近、立ち上げから行ったひと研究の活動成果が事業部から評価され、お客さまへの提案資料に直接採用されたことです。事業部にはない、ひとのメカニズム観点から技術力をアピールしました。チーム全体の努力の結果であることはもちろんですが、アカデミックな知見を活かして事業貢献できたことは、大きな成功体験となりました。
──仕事での経験を通じて得た価値観があれば教えてください。
楽しんで仕事をするためには、個人の気持ちだけでなく周りの働く環境が重要だと思います。ひとのミスはどうしても起こるものですが、環境を整えることで少なくすることはできる。
さらに、活躍や成長ができるか、ひいては人生がよりよいものになるかどうかにもつながると思うんです。自分自身だけでなく、ひとに活躍を促す時にも、自身で環境を作るという点は重視しています。
仕事も趣味も全力で楽しめる環境でチームを率い、ひととクルマの関係性を追究したい

──職場の環境で気に入っている点を教えてください。
人間関係の良さですね。良い人材が多く、困ったことや改善提案なども気兼ねなく発言できる雰囲気があります。また、勤務形態も柔軟でリモートワーク制度やフレックス・タイム制勤務制度を導入しています。おかげで仕事と趣味のバランスを取りやすく、私自身もゲームや登山、クロスバイク、スキーなどを楽しんでいます。同僚たちも楽器演奏やアイドルの推し活など、充実したプライベートを過ごしています。
そういった熱量の高いひとの話を聞くのもおもしろいですよね。1日のスケジュールの中には雑談をする時間があり、そこで話をしたり、たまに出社したり食事をしたりなど、業務以外のコミュニケーションも図っています。
──自己研鑽の機会はありますか?
社内にはさまざまな研修制度があり、チームでもそれぞれ必要なスキルを習得するため、積極的に手を挙げて参加しています。たとえば最近では、UXに関する研修に参加し、ユーザーへのヒアリング手法や課題抽出の方法、解決策の組み立て方などを学び、そこで得た知見をプロジェクトに活かしています。
そのほか、資格取得や学会参加などについても、自身で調べて申請すれば費用を支援してもらえるなど、自己学習を応援してくれる環境が整っています。
──研究における今後のビジョンを聞かせてください。
交通安全に貢献するという目標のために課題となるのが、まずひとの認知メカニズムのさらなる解明だと考えています。人類が長年研究してきた、いわば永遠のテーマですが、どの部分に着目して解明していくかが難しく重要なところです。
さらに、いかにドライバーを楽しませるか。とにかく実際にモノを作って、楽しいか楽しくないかを試してもらい、トライアンドエラーで検証していくことが大事だと思っています。ゆくゆくは、私たちのめざす安全運転の形を通じて、高齢になっても安全に運転を続けられ、認知症予防などさまざまな効果にもつながる。そんな社会が実現できるといいなと考えています。
──加藤さん自身は、今後どういう存在になっていきたいですか?
入社9年目を迎え、研究活動ではリーダーとして、研究の価値やメンバーのマネジメントに責任を持つ役割を担っていきたいと考えています。また、事業への貢献という意味で、研究内容を製品にどう組み込むかなどの調整も今後重要な仕事になると感じています。ひととクルマのより良い関係を追究し、未知の領域に挑戦しながら、安全で楽しい運転の実現に貢献していきたいですね。
他のインタビューを見る
-

岩田 総一朗
ICT(セキュリティ)
2020年新卒入社 -

神山 美奈子
ソフトウェア設計開発
2024年キャリア入社 -

「未知に、駆け出せ。」で世界一に挑戦する組織へ
-

寺村 優希
ICT(ソフトウェア・クラウド)
2023年新卒入社 -

根本 湖輝
AI
2023年新卒入社 -

点在から団結へ、技術系女性社員の新たな挑戦。交流会で生まれる仲間たちの絆
-

澤井 宏和
品質管理・環境
2022年キャリア入社 -

鈴木 美蘭
製造
2022年高卒入社 -

雨宮 瑞希
ひと研究(データアナリスト・ソフトウェア)
2021年新卒入社 -

スー ヅーシャン
機構メカニズム設計開発
2022年新卒入社 -

大谷 壮
製造
2020年高卒入社 -

東山 知彦
ソフトウェア設計開発
2022年キャリア入社 -

馮 少奇
モビリティサービス新規事業開発
2022年キャリア入社 -

松谷 眞克
PM(プロジェクトマネジメント)
2021年キャリア入社 -

栗山 直之
機構メカニズム設計開発
2019年新卒入社 -

小笠原 友恵
DX(データマネジメント/データサイエンティスト)
2024年キャリア入社 -

澤井 駆
情報システム
2020年新卒入社 -

福井 由紀子
ソフトウェア設計開発
2016年 社内公募制度にて転籍 -

八重垣 稜佑
品質管理・環境
2019年新卒入社 -

趙 健淙(Jerry)
ICT(ソフトウェア・クラウド)
2017年新卒入社 -

楠 葵衣
生産技術
2022年高専卒入社 -

杉本 大翔
生産技術
2020年高専卒入社 -

植林 恭子
品質管理・環境
2009年高専卒入社 -

冷水 柊生
生産管理
2022年高卒入社 -

浦添 和哉
AI
2020年新卒入社 -

中野 久幹
AI
2019年新卒入社 -

石井 攻
ICT(セキュリティ)
2018年新卒入社 -

和泉 洸史朗
品質管理・環境
2019年高専卒入社 -

高島 綾
調達
2022年新卒入社 -

奥田 幹也
営業
2020年新卒入社 -
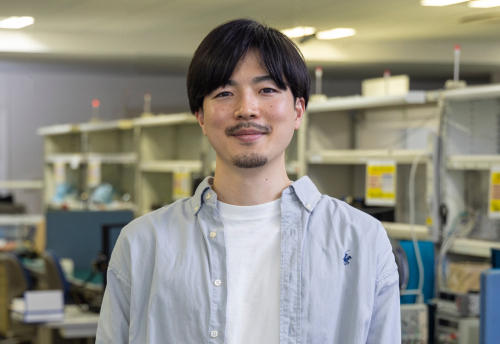
岩佐 惇平
電気設計開発
2021年新卒入社 -

基村 友希
機構メカニズム設計開発
2009年 三洋電機株式会社
(現パナソニックグループ)入社 -

佐々木 薫
人事
2019年新卒入社 -

上田 尚弥
ソフトウェア設計開発
2019年新卒入社 -

水田 健人
ICT(ソフトウェア・クラウド)
2019年新卒入社 -

副業でパワーアップ:業務の垣根を越えて得る、多くの刺激と気づき
※当社企業サイトに遷移
-

副業でパワーアップ:本業に向き合う姿勢も、アグレッシブに
※当社企業サイトに遷移
-

副業でパワーアップ:経営者の視点で、コスト意識が向上
※当社企業サイトに遷移
-

業務時間の最大15%を新たなチャレンジに
-

プレミアムな休暇の過ごし方
※当社企業サイトに遷移
-

今の自分にとってベストな働き方を選択
※当社企業サイトに遷移
-

多様性は方向性や解決策を見出す糸口
※当社企業サイトに遷移
-

障がいを越えて「音のある世界」にチャレンジ
※当社企業サイトに遷移







