Newsroom
自ら学び教え合う 企業内大学PAS Universityとは?
2024年10月、パナソニック オートモーティブシステムズに、企業内大学「Panasonic Automotive Systems University(以下 PAS University)」が設立されました。「自ら学び教え合う」というコンセプトのもと、社員の能力・スキル向上や自律的なキャリア形成支援を目的としたPAS Universityについて関係者4人に取材しました。専門家育成のコミュニティ編成・人財育成の取り組みの中から、UXデザインとAI講座についてご紹介します。

PAS University設立の背景を教えてください。
樋口:当社は2022年4月の事業会社化に伴い、人的資本経営の強化を目的とした人事制度改革を進めてきました。「人財育成に最も強い会社」を目指すというポリシーのもと、社員の自律的なキャリア形成を支援するため、それまで部門別の研修制度を統合してコーポレートとして強化する狙いでPAS Universityを設立しました。
PAS Universityの特長は何でしょうか?
樋口:当社は、経営理念の一環として人財育成を大切にしており、各部門がしっかりとした研修基盤を築いてきました。PAS Universityはこれまで培った育成基盤をすべて踏襲・包含する形で、幹部をはじめ関係者が教えることの大切さを定期的に発信することで「自ら学び教え合う」という学びの循環を促進し、個人が保有する知識やノウハウに加えて最新の技術を迅速に学べる環境を作り出すことを狙いとしています。
誰もが講師・受講者になれるPAS Universityでは、自らを多角的な視点で見つめなおす機会が提供され、新たな学びの意欲を生み出しています。また、最前線で仕事をする現役社員が講師となることで、社内の専門知識を活かしつつ、技術変化が激しい自動車業界のトレンドに合わせて、社外では得られないスピード感ある研修を提供します。
講師陣には、車載機器開発に関わる専門家はもとより、パナソニックのデジタル家電や携帯電話の開発を経験した人財が数多くいます。例えば、これまで家電や携帯電話等の多くの技術が車載機器に搭載されてきました。パナソニックでこれらの開発を経験してきた技術者が、そのバックグラウンドをベースに車載機器開発に携わることで得た知見を教えることができる点も大きな強みと言えます。

受講・講義したきっかけは何でしょうか?
矢谷:私はAI技術の進化が激しい中、エンジニアのAI知見を学会レベルに保つ必要性を感じ、積極的に自分が所属する部門の勉強会で講師を務めていました。今後、車載機器では運転支援等でAI技術が搭載される機会が増えていきますので、当社内でもAI技術のすそ野を広げていく必要性があると考えています。最近は、他部門のメンバーにもOJTを通じてAI技術を広め、車載機器の運転支援技術に対応できるよう活動しており、そのような経緯から講師として関わるようになりました。
小林:私は前職で携帯電話の開発に関わっていた際にUXデザインの大切さに気付き、独学で学んでいました。この会社に来てからも自分の部署でUXデザインについて教えていましたが、これを部署内だけで留めるのはもったいないなと考えていました。そこへ講師のお誘いを受け、「これは参加せねば」と思った次第です。
飯野:営業部門から事業部へ異動することになり、担当業務が商品企画の仕事へ変わったことがきっかけです。商品企画として新規商材を検討する中で、お客様にとって嬉しい体験を設計するUXデザインについて学べる場があると知り、その講座を受講することにしました。継続的に受講する中で、UXデザインを専門とする職種であるUXデザイナーへの興味がわき、社内異動を希望して新事業のUXデザイナーとして仕事をすることになりました。受講が新しい職種への挑戦につながったのです。

受講・講義した感想を教えてください。
飯野: 講座には座学のほかにワークショップやグループワークでの実践もあります。体系的に実践できる場が学ぶ上でとても役立ちました。マインド醸成の内容もあり、座学だけでは身につかない実践力が身に付きました。現在、私はSaaS事業のサービス開発に関わっているのですが、お客様の課題抽出・ユーザビリティ評価の手法などが実際の業務に役立っています。
小林:講義をすることが実践経験を振り返るいい機会になりました。人に教えるからには、ちゃんと教えないといけない。そのためには、言語化しないといけませんし、自分を振り返って、まだまだ勉強不足と痛感しました。それが、自分の学習を再開するきっかけにもなりました。また、受講者の声を受けて、自分とは違う考え方に気づくこともできました。この経験は、ユーザー体験の想定幅を広げることに役立っています。
矢谷: AI技術を解説するために論文を読み、実際にAIを動かすことで自分のスキルアップを実感しています。また、本業でAI開発を行う際にも、その成果物を他の人が活用することをより意識するようになりました。受講者からの鋭い質問やトレンドの追跡が刺激となり、最新技術をより意識するようになりました。AIについて学びの意識が浸透することで、自部署のチーム全体で最先端技術を追求する風土が整い、新たな取り組みも促進されています。先行開発や商品開発のOJTを通じて、学び合いながら進めるようになってきていると思います。
PAS Universityの良さは何でしょうか?
飯野:社員が講師を務め、「教える」視点での知見やノウハウを蓄積しているところです。受講者が講師になることも推奨されているので、組織として自律自走できる仕組みになっていると言えます。受講者だった私も、今では講師を務める機会が増えてきています。受講者が講師になることで、教えられる立場の人間がどんどん増えていき、社員のさらなるスキルアップに繋がっています。
矢谷:まさに、「自ら学び教え合う」というコンセプトだと思います。私は、プログラミング学習のコミュニティを運営してきましたが、受け身の学習よりも教え合うことで楽しく効果的に学べると考えています。今後は、スキルを”教え合う”ことが当たり前の風土をどんどん発展させていきたいですね。
小林:社内コミュニケーションの円滑化にもつながっていると思います。講座に参加すると部署を跨いださまざまな横のつながりができます。通常業務では会わないような他拠点の社員とも交流する機会が増えます。こうなると通常業務のちょっとした相談もしやすくなります。結果として全社の業務の効率化につながっていると思います。

今後、仕事をする上でこうしたいという展望や、さらに学びたいことはありますか?
飯野:人に教えられるスキルをさらに身に着けたいです。社内外の人に自分の学んだことを共有し、一緒に成長していきたいです。また、学んだことを業務に積極的に取り入れていきたいです。UXデザインだけでなく、AIに関する知識など、今後必要になるスキルを身に着け、アウトプットの質を上げていきたいです。
小林:人起点でのUXデザインの考え方を社内全体に浸透させたいです。PAS Universityのミッションとして、社内浸透のための最善策を考え、一つひとつ取り組んでいきたいです。
矢谷:AIやソフトウェアは進化が激しいため、技術を高め合い、常に最新技術をキャッチアップできるチーム作りを目指したいです。今後、当社はソフトウェア技術領域にさらに力を入れていきます。ソフトウェア人財育成活動にも積極的に取り組み、貢献したいと考えています。
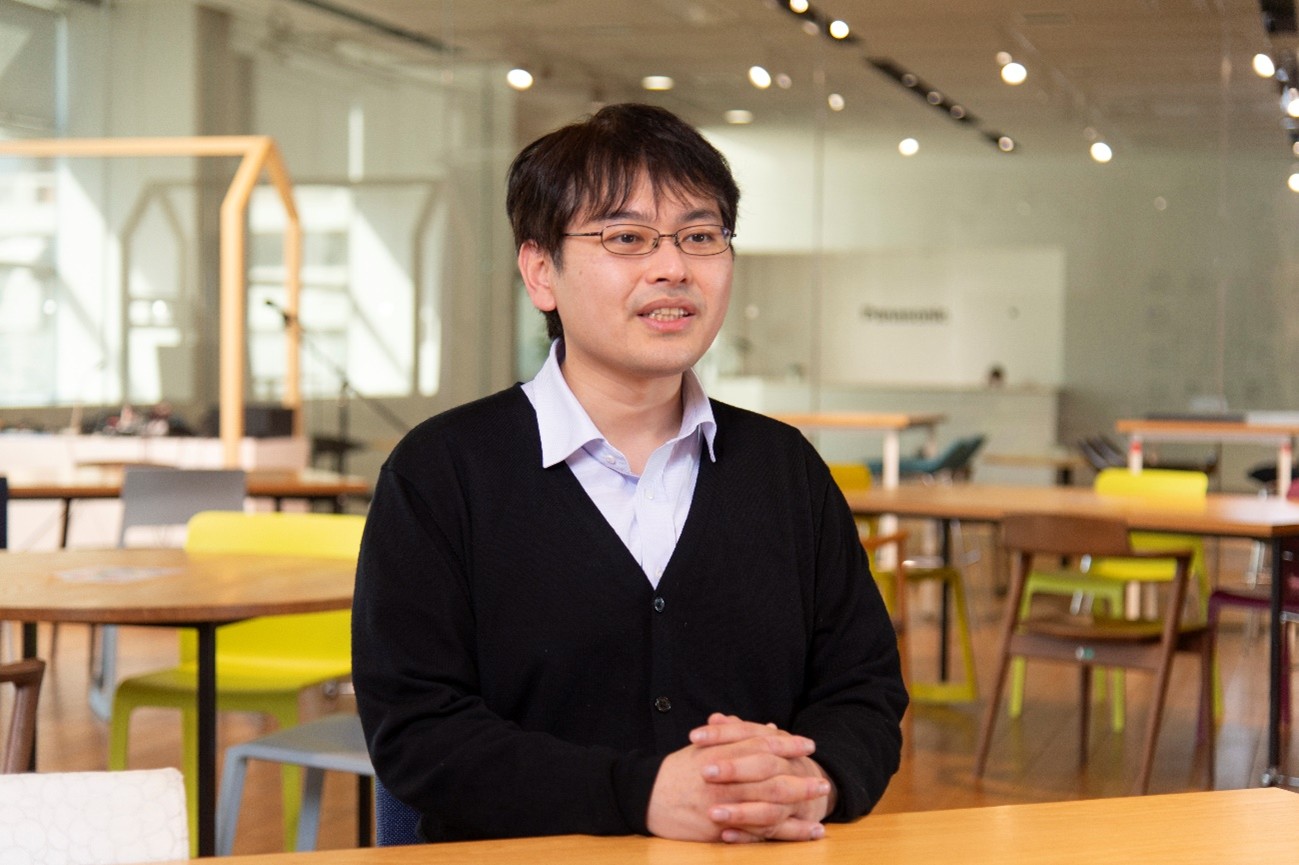
PAS Universityの今後の展望を教えてください。
樋口:研修を提供する場としての役割を果たすだけではなく、事業戦略や技術戦略に沿った人財育成プランを策定し、当社ならではの人的資本経営を実現すべくPAS Universityを成長させていきたいです。従来の授業型の研修スタイルに加えて、相互に学び合うラーニングコミュニティを形成し、全員が学び・教える相互コミュニケーションによる学びの場を提供します。並行してグローバルの拠点との連携も進め、異文化交流を含めた人財育成の幅を広げていきたいと考えています。また、企業内大学間の連携を視野に入れた社外との交流も始めています。
2027年4月、
私たちはモビテラ(株)に、
社名変更いたします。

2027年4月1日、パナソニック オートモーティブシステムズ(株)は、
モビテラ(株)に社名変更します。新社名に込めた想いや、
新しく生まれ変わるロゴマークについて、プレスリリースにてご紹介します。
