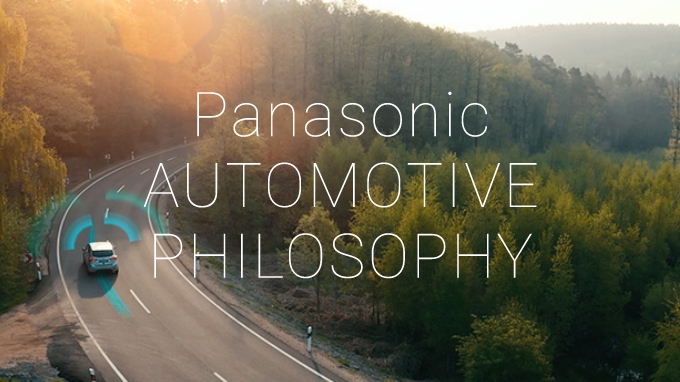パナソニック オートモーティブシステムズは、クルマに乗るユーザーの「体感」に寄り添い、だれもがここちよい「至福の空間づくりを目指しています。今回は、その中でも車内の「音」に注目。不要なノイズを取り除き、耳に届く音を調整。心を動かす音響空間をつくる――車内音響のスペシャリスト3人に、技術の裏側と将来の展望を聞きました。
不快な音を取り除き、
音響空間のベースをつくる。
谷さんは、乗員に静かな車内環境を提供する「アクティブ・ノイズ・コントロール(ANC)」などを担当されているそうですね。
谷
はい。車内のノイズを抑える方法は、大きく分けて2つあります。ひとつは、エンジンや路面からの振動や騒音を吸音材や構造で抑えるパッシブ(受動的)な方法。もうひとつが、マイクで拾った騒音に対して同振幅・逆位相の音をスピーカーから出力し、アクティブ(能動的)にノイズを打ち消すANCです。私はこのANCを中心に担当しています。
車内音響を語る際、なぜ「ノイズを抑えること」が大切なのですか?
谷
クルマに乗るとき、人は騒音が大きいとストレスを感じ、疲労に繋がるからです。同乗者との会話がしにくいことも、ストレスを増加させます。クルマのノイズには、エンジン音、ロードノイズ(路面音や走行音など)、そして風切り音の大きく分けて3種類ありますが、どれかひとつを抑えても他が目立つ、いわば「モグラ叩き」のような状態になります。ですから、全体的なバランスをみながらノイズを抑えていく必要があります。
とはいえ、単なる無音を目指しているわけではありません。安全に運転するためには、加速感や接地感を伝える音など、必要な「音」の情報があります。これらを消してしまうとクルマの挙動がつかみにくくなり、かえって危険です。私たちが追求するのは、必要な音情報は残し、頭の周りにまとわりつくような不快さを取り除いた「質の高い静寂」です。


逆に、あえて「音」を強める場合もあるのですか?
谷
そうですね。例えばスポーツカーに乗るユーザーには力強いエンジンサウンドを好む方もおられます。当社のアクティブ・サウンド・コントロール(ASC)を使えば、エンジン音のないEVにあえてエンジン風の加速音を加えるなど、音響の演出も可能で、個別のクルマのブランドイメージに沿った音を加えることもできます。もっとも、将来、完全な自動運転が当たり前になれば、本当に静かな車内空間を提供する方向に変わるのかもしれませんね。
「質の高い静寂」の
先にある、
心を動かす音づくり。

浅海さんと大友さんは、車内の音響を整える役目ですね。
浅海
私の担当は、車内の音響チューニング全般です。実は、クルマは音楽を楽しむ環境としては、あまり適していません。そもそも移動するためのもので、音を聴くことが優先される空間ではありませんからね。走行性能や安全性を担保するための構造があって、軽量化もされるわけですから。それでも、クルマに乗っている人たちに、できるかぎりよい「音響体験」をお届けするのが、私たちの役目です。
大友
私は、スピーカーの設計を担当しています。車内に取り付けるスピーカーは家庭用オーディオのスピーカーと異なり、耐久性や搭載面、コスト面などさまざまな制約があります。特に搭載面に関しては大きな制約で、家庭用オーディオのような大きな箱に収めたスピーカーを搭載することはできません。それらを踏まえて、チューニングエンジニアの思いを忠実に表現できるよう、ハイパワーでも歪まずに安定して音楽を再生するなど、良い音を実現するようなスピーカーを設計しています。実はスピーカーの基本構造は約100年変わっていない製品です。一見進化が無いようにも見えますが、車載という制約の中で、より良い音の実現に向けて極めることは実はとても奥が深いのです。
具体的に、クルマで音楽を楽しめるよう、どのような工夫がなされているのですか?
浅海
先ほどスピーカーのエンクロージャーの話も出ましたが、クルマのスピーカーって、たいていドアやダッシュボードについていて乗員に極端に近い位置についていますよね。ふつう、ステレオで音を聴かせるには、人の正面寄りから、左右等距離に2つスピーカーを置きますが、クルマでは乗員はクルマの中心には座れないので、それができない。どうしても近いスピーカーの音ばかり聞こえてしまいます。どの席からでも、人の耳にちゃんとステレオの音を届けるのには、さまざまな調整が必要です。基本的には、停車した状態でベストパフォーマンスが出せるように調整した上で、走行中もちゃんと音楽が楽しめるようにしていきます。例えば、エンジン音やロードノイズにマスクされないように意図的に低音を強く鳴らす、というような工夫がされているんですよ。
大友
スピーカーの位置に関して、家庭用オーディオの場合はスピーカー位置を比較的自由に最適な設置ができますが、どの位置で聴くかは人任せです。逆にクルマの場合、スピーカーと人の位置関係はきちんと決まっています。そのため、私たちプロがそこに狙いを定めてつくり上げた音響空間を再現性高く楽しめるというクルマならではのメリットもあります。ノイズの発生源があらゆる箇所に存在するクルマは、音響空間をつくり上げるには難しい環境ですが、むしろプロのチューニングをダイレクトに楽しめます。


クルマという厳しい環境下でも「音」を追求する理由は何でしょう?
浅海
現在の住環境では、大きな音量で音楽を楽しめることは少なくなりました。専用のリスニングルームがあるなら別ですが、たいていの場合はイヤホン、ヘッドホンで音楽を楽しむのが普通です。クルマは、耳を解放してオープンな環境で音楽を楽しめる貴重な空間です。だからこそ、移動の空間で特別な体験ができるよう、いい音響空間を提供したいのです。
大友
私はもともと音楽が大好きで、趣味で曲づくりもしています。クルマに乗るとすぐ音楽をかけますし、今までの旅の思い出にも、そのときかけていた音楽が紐付いて記憶しています。昔のプレイリストを見ると、その当時見ていた風景や気持ちが、鮮やかに蘇ります。「音響」は移動体験をより豊かにしてくれるのです。だからこそ、車内の音響にこだわっています。
音響がもたらす、
未来の「移ごこち」とは。
最後に、未来のモビリティ体験において、音響や「音の環境」はどのように進化していくとお考えですか?
浅海
高度な自動運転が当たり前になると、人は運転から解放されて、自由に移動空間を楽しむことができます。そうなると、よりエンターテインメントを楽しむ空間としての価値も高まり、音響もより臨場感を重視した方向に進化するかもしれません。技術面では、映画館で導入されているような立体音響技術がクルマ向けとしてより進化していくといった未来が訪れる。なんてこともあるとおもしろいかもしれませんね。
大友
立体音響のほかに注目すべきは、パーソナライズ、「音響の個別最適化」ですね。ドライバーが聴きたい曲と助手席やリア席で聴きたい曲が違っても対応できるとか。一緒にクルマに乗る友人と聴く良さもありますが、飛行機のように、各座席個別で聴く、見るということもできるでしょう。
谷
音響の個別最適化は、音楽だけに留まらず、エンジン音などのクルマそのものの「音色」のデザインにも広がりつつあります。
運転を楽しみたいときは、チューニングされた気持ちいい加速サウンドを響かせる、音楽を楽しみたいときなどは、ロードノイズなどの騒音がコントロールされた静粛性の高い空間を確保する、というふうに、ひとくくりではなく様々なニーズに対応できるようになるでしょう。私たちパナソニック
オートモーティブシステムズは、これからも音響技術を通じて、「移ごこち」をデザインしていきたいと考えています。
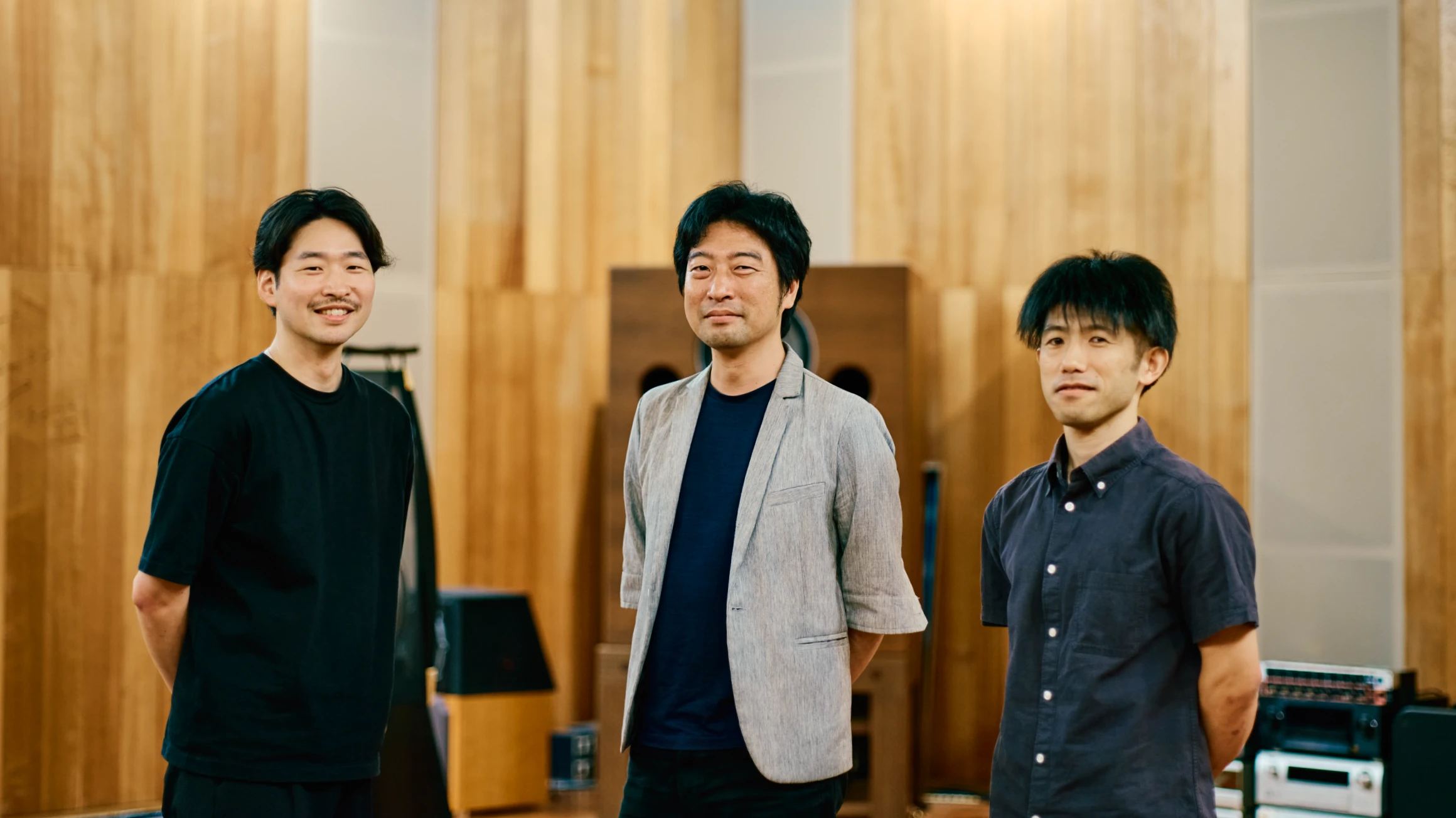

谷 充博
2010年に入社し、開発本部、事業部に所属。以降、現在までロードノイズANCを中心とした音響制御製品の先行開発に従事し、基礎開発から量産立ち上げまで広く担当。低ストレスな移動空間の実現に貢献することが目標。
ここちよさを感じるのは?
趣味のボルダリングで岩と向き合っているとき。
浅海 健
2006年にパナソニックITSに入社し、2009年まで電気設計部門にてオーディオの開発に従事。2010年以降、現在まで音響要素開発を担当しプレミアムサウンドシステムの音響チューニングやシステム設計開発を担当。移動時間をより良い音を聞ける環境にすることで移ごこちに貢献することが目標。
ここちよさを感じるのは?
朝、会社に来る前にカフェでコーヒーを飲みながら読書をしているとき。
大友 景太郎
2018年に入社し、現在までスピーカ開発部門にて車載スピーカの設計に従事。標準スピーカ、プレミアムスピーカ等様々なスピーカの提案から基礎設計、量産立ち上げを担当。音を通じて感動の移動体験を創出することで移ごこちに貢献する事が目標。
ここちよさを感じるのは?
音楽を聴きながらゴロゴロしている時間。